ゼミブログ
AIを学習に活かせる人はどんな人?|長岡校
2025年11月14日
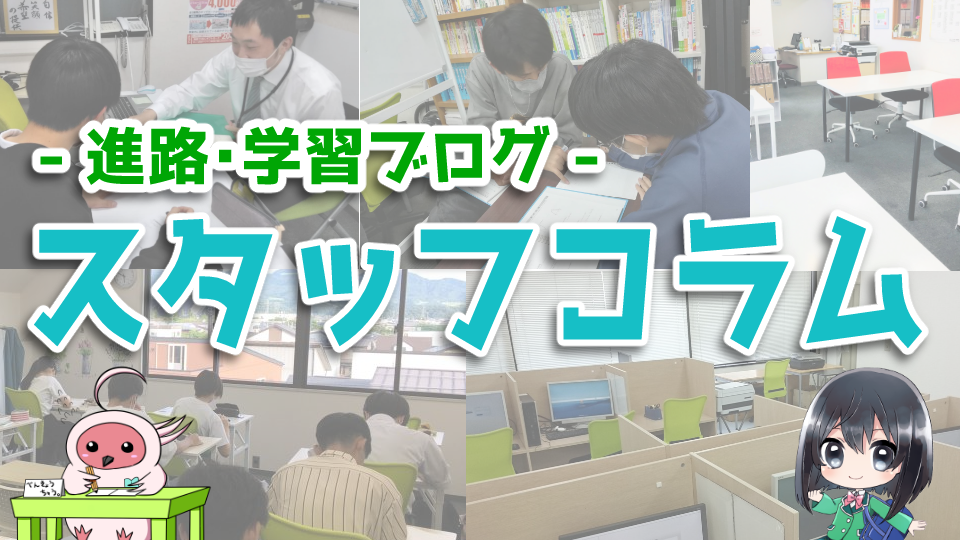

こんにちは。
真友ゼミ長岡校の山口です。
今日は普段の勉強の話は少し置いておいて、AIについて気になった話題に触れたいと思います。
最近何かと話題のAI技術ですが、今の中学生や高校生にも聞いてもらいたいと思いますので、ぜひ一緒に考えていきましょう。
AIをうまく使える人・学習に活かせる人

先日、東京大学の広報誌にて、経済学部の教授が寄稿されたコラムが話題となりました。
内容を要約すると、
『経済学を全く勉強していない専門外の学生が、生成AIを利用して学術誌に掲載できるほどの優れた論文を作成してきた』
とのことです。
これだけ聞くと、AIの性能がそこまで進歩しているんだな~、で終わりそうなのですが、大事なのは次の2点です。
一つ目は、この学生のマネジメント能力です。
AIは一見すると優秀に思えますが、実際は人が与えた問題に、“それらしい”答えを返しているに過ぎません。
ユーザーの知性に合わせて返答している以上、基本的にAIの性能はユーザーに依存します。
この学生は、研究テーマ出し、先行研究、そこから何が言えるか、どんな反論があるかなど、都度適切にAIを利用していたと思います。
ここでユーザーが行うべきは、AIが出力したことを評価したり、反論したりするのではなく、それらをAI自身が行うようディレクションしていくことです。
AIの得意とする分野と人間の得意とする分野を適切に把握し、上手にAIを活用したと思われます。
二つ目が、この学生が論文を作成した後に、専門家にチェックを受けていることです。
上のリンクでも、学生自身が言っていますが、
『AIとの対話の中では、国際誌に通用する水準と評価されたものの、自身には経済学の素養がないため、その評価が正しいのかわからない。自分が知見の無い分野でのAIの判断が正しいかどうかをどうやって確かめるとよいのか。そのひとつとして、経済学の教授に意見を求めてみた』
繰り返しになりますが、AIは“それらしい”答えを出力しているだけなので、中にはとんでもないことを述べている可能性もあります。
果たしてAIが述べていることが正解なのか間違いなのか、この学生のように専門外の研究に手を出している状況では判断しようがありません。
じゃあどうするか?
簡単です。
わかる人に聞いてみればいいんです。
前回のブログでも紹介しましたが、大事なのは“メタ認知”です。
これは自分の考え方や行動がどのように見えるか、客観的に観る能力ですが、AIを利用する場面でも同じことが言えます。
AIが出力した答えが正しいかどうかを客観的に判断するのもユーザーのメタ認知力次第です。
高校生や、早い子なら中学生でも生成AIに触ったことがある子もいるでしょう。
今の中高生はAI世代と言われるように、皆さんが社会人になるころには今以上にビジネスや学習、研究の分野でAIが浸透していることでしょう。
だから、皆さんがAIを“使えない”というのは論外として、どう使いこなすかが問われる世代になります。
AI時代に必要なのは、マネジメント能力とメタ認知力です。
これを鍛えることでしか、あと10年もしないうちにやってくるAI全盛の波を乗り切ることはできないだろうな、と思います。
 | ◇真友ゼミ長岡校◇ 長岡駅東口から徒歩5分!長岡市・見附市・小千谷市からのアクセス抜群!「赤点・E判定からの大学受験」をモットーに、勉強に対して不安や不足を抱えている中学生・高校生を全力サポートする個別指導塾です! 真友ゼミ長岡校についてはこちら |
